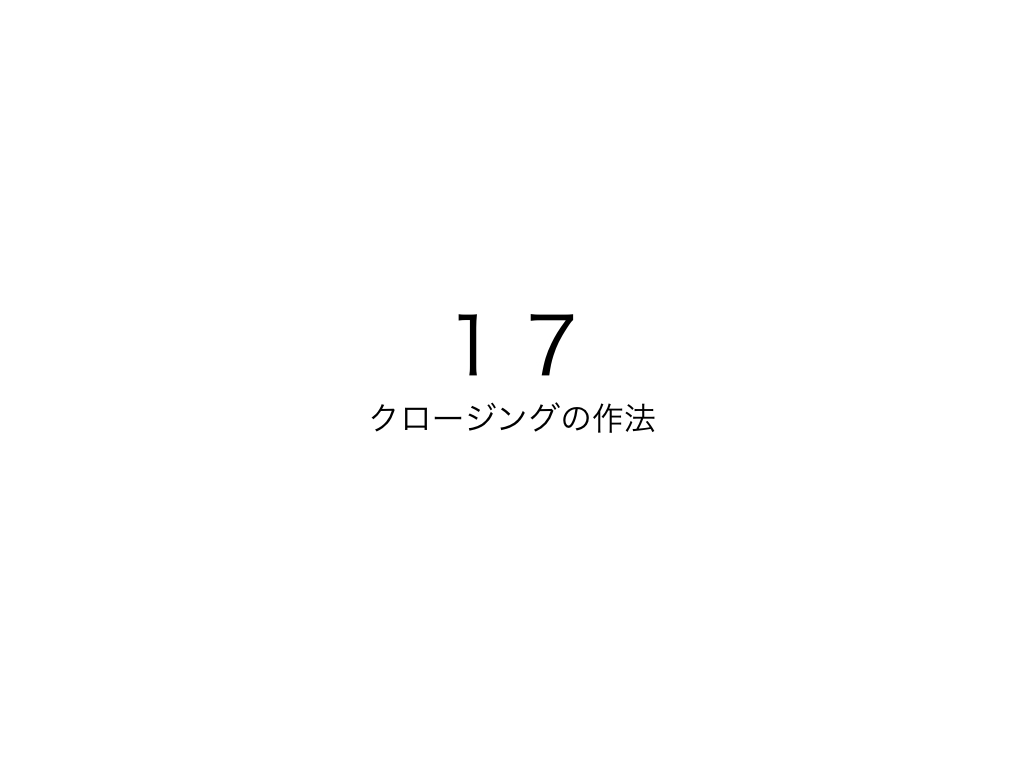最後にポジティブな印象を残し、プレゼンの効果を高めるための手法を紹介します。
AUDIO
(トータル時間 (04:33)
TEXT
余韻を残してきちんと終わる
このページではクロージング、つまりプレゼンの締めの作法についてお伝えします。「作法」と表現しましたが、決まったマナーがあるわけではありません。しかし、心理学には「親近効果」と呼ばれるものがありますが、これは物事の最後の部分が特に印象に残りやすく、その結果、全体の評価に大きな影響を及ぼすという心理現象です。例えば、講演やプレゼンテーションの終盤が素晴らしいと、全体を通して良い印象を持ちやすくなります。同様に、最後の部分が悪いと、全体の印象も悪くなりがちです。終わり方が重要です。
ここでQ&A/質疑応答と、プレゼンを終わるときの最後のあいさつについて注意ポイントをお伝えします。
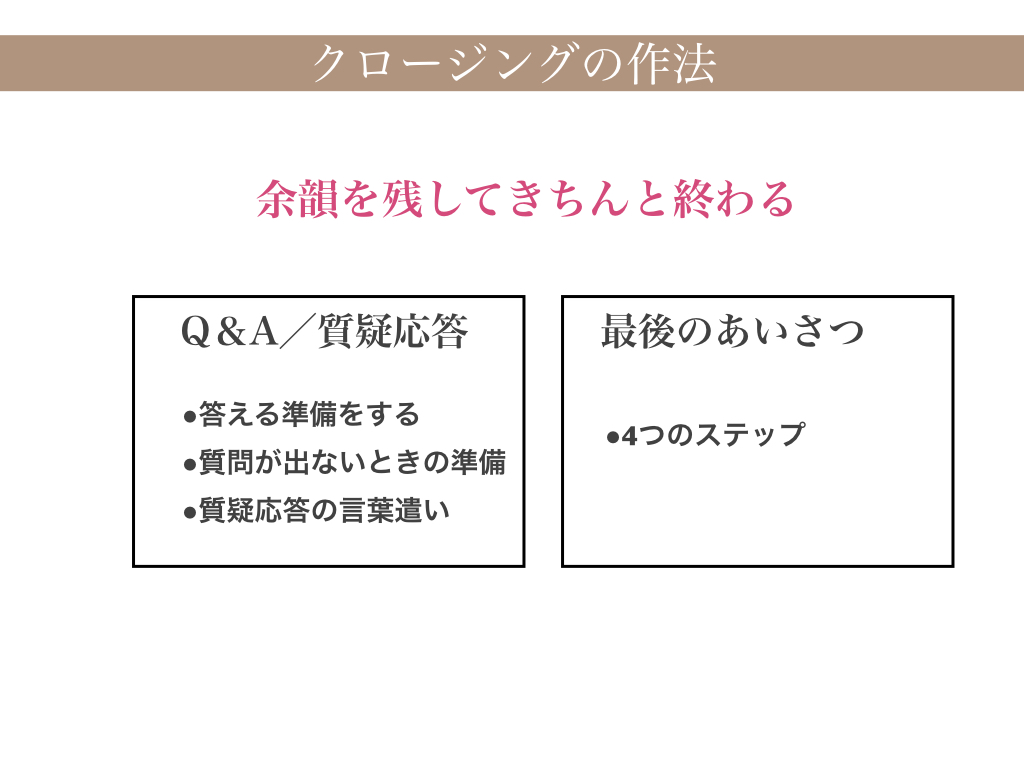
Q&A/質疑応答の注意ポイント
質疑応答の注意ポイントは、以下の3つです。
●答える準備をする
●質問が出ないときの「よくある質問とその答え」も準備する
●質疑応答の言葉遣い
以下、詳しく説明します。
答える準備をする
あらかじめ出そうな質問に対する答えを用意しておきます。重要なプレゼンであれば、チームでブレーンストーミング形式であらゆる質問を出し、それを整理して応え方や必要な補足データを準備しましょう。
特に「反論処理」と言われる準備が大切です。これは、用意した提案や結論に対してネガティブな意見が出されたときの受け答えを用意しておくことです。用意するのは文言だけでなく、相手の反感を誘わない受け答えの練習やネガティブな意見に耐えるためのメンタルコントロールも重要です。
質問が出ないときの「よくある質問とその答え」も準備する
聞き手が消極的なときもあり、質問が全くでないことはままあります。この場合、「質問が出ないなら終わります」とするよりも、よくある質問に答える形で、伝えたいことを強調する時間に使うのが要領の良いやり方です。3問ほど「よくある質問とその答え(言いたいこと)」を用意しておけば十分でしょう。その質問や答えに刺激された他の聞き手が質問を考え付くこともあります。
質疑応答の言葉遣い
先に言った「親近効果」のように、終わりのほうの印象は残るものです。質疑応答の際の言葉遣いで印象を悪くしないように気を付けてください。聞き手の立場や年齢などに関わらず、言葉遣いは必ず丁寧語(です・ます調)にし、質問にはお礼の言葉を欠かさないようにしてください。
質問への答え方は以下の4ステップです。
1)質問への感謝
「ありがとうございます」
2)質問内容の確認と御礼
「~というご質問でよろしいですか?」「ありがとうございます」
3)回答
※できる限り、相手が使った言葉を使って答える。
4)同意を得て御礼で終わる
「ご質問への答えになりましたか?」「(相手が同意したら)ありがとうございます」
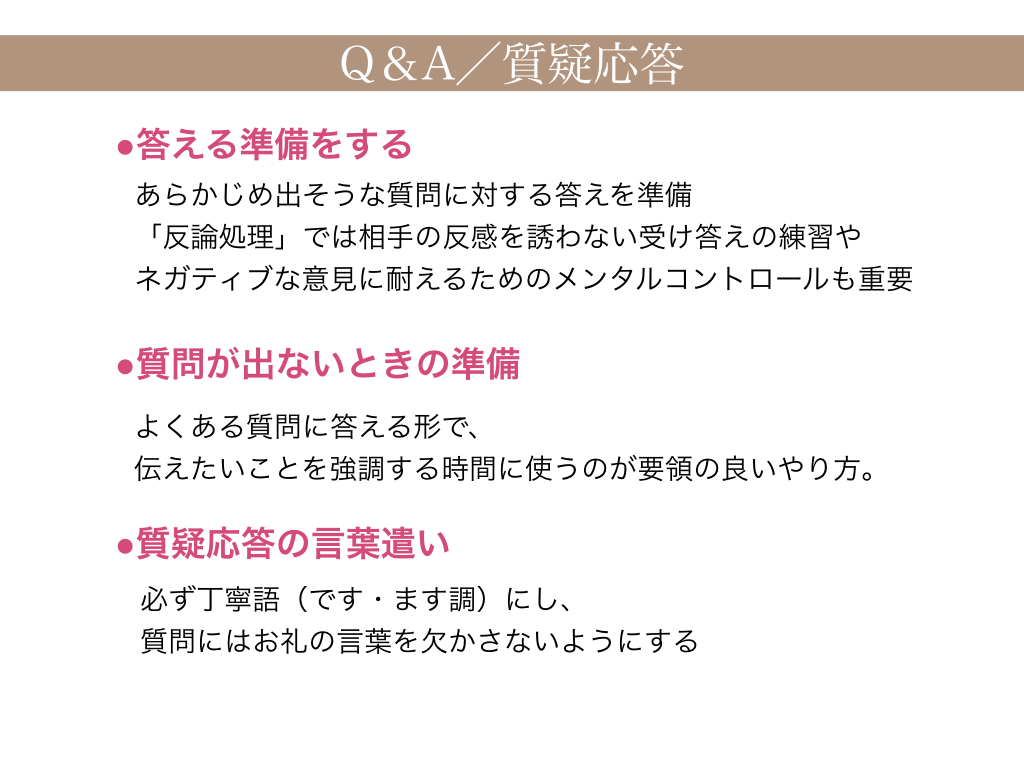
最後のあいさつの注意ポイント
最後のあいさつは、話し手の印象の余韻を生むものにもなります。味気ない終わり方をしないように注意してください。以下の4つのステップを意識しておいてください。
1) 締める意思を伝える
(例)「では、質疑応答はこれくらいにしたいと思いますがよろしいでしょうか」
2)内容を一言でまとめる
(例)「今日は〇〇について〇〇のお話をさせていただきました」
(例)「ここまで〇〇のご紹介をしました。皆様に〇〇となることを祈っています」
3)締めの言葉
聞き手のほうを向き、微笑んで御礼の言葉で締める
(例)それではこれで私の話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました」
4) お辞儀をする。
きれいなお辞儀をして聞き手をまっすぐ見て笑顔を見せてください。
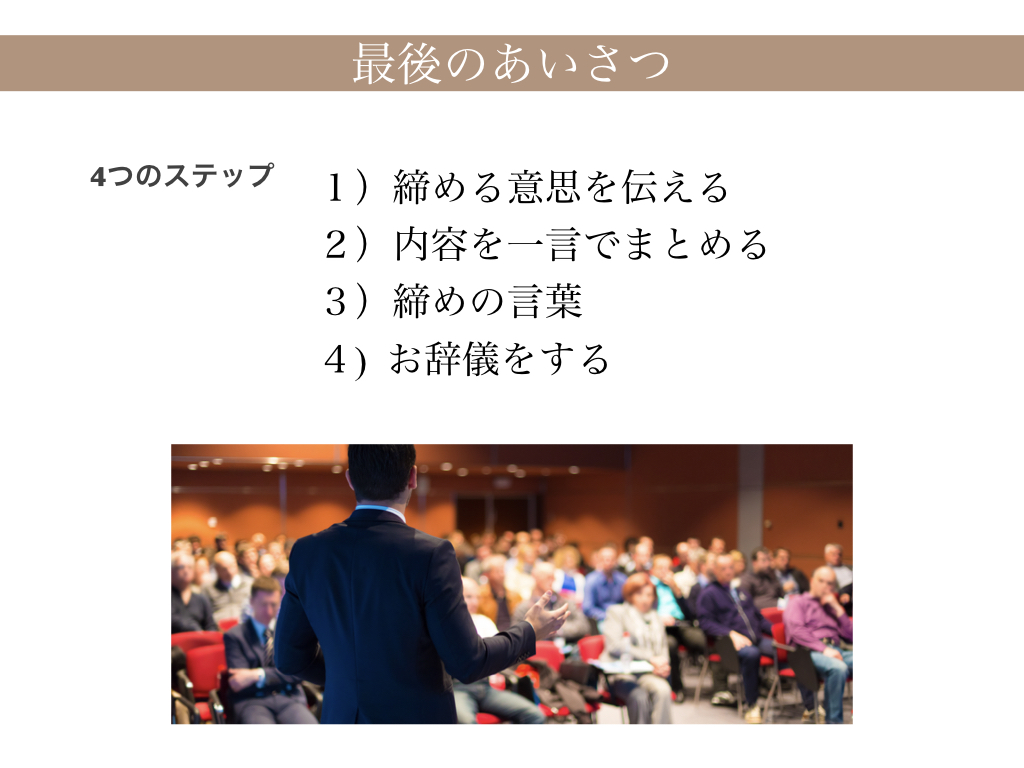
いかがでしょうか。終わりよければすべて良しではないですが、終わりの印象でプレゼン全体の印象もだいぶ変わります。このページにあることはきちんとした作法として意識し、終えるようにしましょう。